人生と学び
色を探す旅 ~講演会「芸術が海を渡るとき」を聞いて~
『インディゴを探して』
志村ふくみさんの帯メッセージより
2020年12月18日、本学の非常勤講師クララ・キヨコ・クマガイ先生原作の絵本『インディゴを探して(原題:A Girl Called Indigo)』の翻訳出版に際し、オンライン公開講演会「芸術が海を渡るとき」が開催されました。
この講演は、お父様が日本人のルーツをもつアイルランド人作家 クララ先生と、染織家 志村昌司さんの対談、小学館編集者 喜入今日子さんにお話をお伺いする企画です。2019年度の津田塾祭にて、英語英文学科特設プログラムである翻訳・通訳プログラムの学生や大学院生を中心としたPeace Art Projectが実際にこの作品の翻訳に挑戦しました。“Journey of Colours”と題する展示では、学生たちの翻訳の展示や物語にまつわる装飾、北欧音楽バンドをお招きして、物語の朗読に音楽を乗せる演奏会などが催されました。
このように津田塾とも縁が深いクララ先生の絵本は、志村昌司さんのおばあさまとお母さまであり、染織家であられる志村ふくみさん・洋子さんの染めに着想を得て誕生したおとぎ話のような物語です。特に、クララ先生が感銘を受けたのは、2014年に人間国宝である志村ふくみさんが京都賞を受賞されたときのスピーチとのこと。「色を生きたものと捉えるふくみさんのお話を伺って、自分の色に対する考え方が変わった」とおっしゃるクララ先生は、まるで自然の生きものを相手にするかのように色に接する少女インディゴを生み出します。
本講演は一冊の絵本から広がる縁で結ばれた方々を中心に、藍染めのお話、人間と自然の関わり、絵本の出版についてのお話など、くるくると表情を変える自然の色のような多彩なお話を伺う貴重な機会になりました。
今回のplum gardenでは、その講演会のほんの一部をお届けします。
むかしむかし、ある日のこと。草木や水などの自然に溢れる色を愛し、自然から多彩な色を誘い出すことが得意な一人の少女インディゴのもとに王様から「永遠の命をあたえる色」を探せ—という依頼が舞い込みます。そんなことはできないと言うインディゴでしたが、たしかに一つ、心当たりのある色がありました。
(絵本より抜粋)
夕暮れ時、日が沈んだほんの少し後の空の色。
「夜明けのハーブ」との二つ名を持つブルー・マローの花びらの色。
あら、これは物語には出てきませんね。
藍の命を育む
さて、まずはそんな藍色を、糸に染み込ませる藍染めのお話から。
藍染めは布を染める前、植物から藍の色を作る工程「藍建て」から始まります。
新月。乾燥させたタデ藍を水で発酵させてできる蒅すくもに、あくとお酒、ふすま(小麦の殻)を混ぜます。この工程が「藍建て」です。それは、単に植物を潰して染料にするということを意味するのではありません。まるで生きものに対するかのように「藍さん。藍さん」と呼びかけるという志村さんご一家は、藍を染料や植物ではなく、私たちと同じ生き物だと思うことで藍独特の色が出ると感じているそうです。毎日壺をかき混ぜたり、温度管理をしたりと気を配って、子供を育てるように藍を育んでいく。そうして次の満月になると、布を染め始めます。このように、藍染めは太陰暦—月の満ち欠けに呼応させる形で進められるのです。
一つの壺に入った藍の染料ですが、時間とともに勢いのある若い色から壮年期の渋い色に変わり、次第に透明に薄れ、最後は色が消えて糸が染まらなくなると言います。藍の成熟段階に応じて、色を変えていくその様はどれも美しく、まるで人間の一生を見ているよう—だから、藍染めは命を育む行為なのだと、そして、その自分以外を大切にする行為は現代人にとって必要なものではないかと、志村さんは語ります。
つまり、命の数だけ色がある。
—志村ふくみさん・洋子さんの
ドキュメンタリー映像
Colors of Lifeより抜粋
藍の命の神秘さは糸を藍壺に浸けて、壷から引き出したほんの一時、糸が緑色に染まる瞬間にも感じるようです。草木染めは一つひとつ、異なる植物から色を引き出すため、多彩な色の陰影を出せるそうですが、その中で唯一表現することができない色が緑だと言います。その色が、布が藍色に移り変わるまでの一瞬、緑色に染まるというのですから、まさに緑の不思議ですね。
私たちと自然の関わり
(出典『染織講社紋章縁起書』)
このように、ある時は植物を染料に、またある時は生薬とするなどして、人間の営みは行われてきました。
人間の活動が地球規模に拡大し、近年、重大な地球環境問題に陥っています。そのような時代の中で、志村さんは自然と人間を介する技術として、近代を見直し、それ以前のものに思いを至らすべき時が来たのではないのかと感じているそうです。
「都市や町に住む人が増えて、どんどん自然との距離が開いていく私たち」に危機感を覚えているというクララ先生と同じく、「草木染めは自然があってこそ。自然を尊重することが大切」と日々感じている志村さんですが、このデジタルの時代に一つの希望を見出していると言います。デジタル・ネイティブである若い世代の人と話すと、インターネットを通じて意識が世界に広がる良さがあり、国境を越えた活動に取り組みたい人が増えていると感じることがあるそうです。植物に国境がないように、人間にも国境がない、と訴える志村さん。地球規模での環境問題を考える必要性と、その可能性を改めて示唆してくださいました。
色を探して
『インディゴを探して』の出版を手がけられた小学館の喜入さんからお伺いした、出版における裏エピソードも少しお見せしましょう。
この物語を最初に読まれたとき、「たくさんの色が登場する、この神秘的な物語に、たくさんの色を付けたら素敵な一冊になる」と感じた喜入さん。繊細な色の違いを表現するため、多彩な顔料を用いる日本画がよいのではないかと考えました。そこで、日本画家の横須賀香さんに挿し絵を依頼したところ、「色が溢れていて、読んでいるだけでも想像が膨らみわくわくする」と快くお返事を頂けたそうです。
ところが、クララ先生の物語に色を付けていくとき、横須賀さんがとても悩んだことがあったといいます。それは、「人はそれぞれの色のイメージをもっていて、その色のイメージは生まれ育ったところによって違う。クララ先生がアイルランドの空を見て感じた色と、私たちが東京の空を見て感じる色は違うのではないか」ということでした。
それからは、挿し絵を担当された横須賀さんとともに、色を意識しながら過ごす日々だったと喜入さんは振り返ります。
夕暮れ時、藍色の帳がどのように空を覆うのかを毎日見たり。
志村さんの個展や藍染め体験で、藍が本当に色々な表情を見せるのだと感じたり。
実際に、横須賀さんが挿し絵を描き始めたとき、絵の下地に紫や黄色、青、赤、どんな色を塗っても、その上から塗った藍色は下地の色と共鳴して、さまざまに微妙な表情を出してくれる、そこに藍色の大らかさや懐の深さを感じ、感動したとおっしゃっていたそうです。
コロナ禍で閉塞感を感じる日々ですが、自分の心の声を聞いて、自分に寄り添う色を探すことで乗り越えていけたらと締めくくる喜入さん。
喜入さんと横須賀さんにとって、『インディゴを探して』という絵本の制作もまた、各々の色・色彩感を探す旅だったのかもしれませんね。
ところで、絵本の中、インディゴが藍を探す旅は結局どのような結末を迎えたの?ですって。
最後のページは、インディゴが藍色の空の中にふぅと消えていくミステリアスな場面で終わります。どうしてそのような終わりになるのかは、絵本を手に取って、みなさんがインディゴと共に答えを探す旅に出た先に見つかるかもしれません。
コロナで家に閉じこもりがちな私たちも、夜の帳が包む色や、日が射した昼間の木々の色などを眺めながら、自分の心に寄り添う色を探していきたいですね。






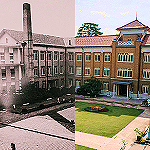

.jpg)