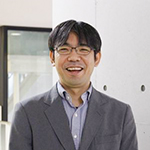人生と学び
人生と学び #21 - あらゆる「暴力」と向き合う 前編
津⽥塾⼤学の学⽣の中には記者を⽬指している人も多いのではないでしょうか。「⼈⽣と学び」第21回では、元朝⽇新聞記者で、現在「マスコミ論」の授業を担当されている川崎剛先⽣にお話を伺いました。今回は前編、後編に分けてお届けします。
前編では、川崎先生の記者時代の経験について詳しくご紹介します。
記者経験
—記者になろうと思った経緯を教えてください。
⼩さい頃から世界への関心がものすごく強かったんです。小学生でアフリカの国の⾸都を全部覚えていたし、外国に⾏きたいと思っていました。新聞社の特派員になるのは夢だったんです。浪人も留年もして社会に居場所がないと感じたこともあるのだけれど、朝日新聞社が採用してくれた時には、その時はどうやればいいかまだわからないけど、できることを⼀⽣懸命やろうと思いました。⾃分の与えられた場所はここかなという感じがありました。
—朝日新聞社に入社後、地方支局に配属されていますね。
1980年に朝日新聞社に入社して、長崎支局に配属されました。地方には、県庁や市役所や大学があって、その地方の政治や経済、文化、スポーツがあります。国や世界の縮図のような取材、記事の書き方、人との付き合い方などさまざまな経験、勉強をします。特に長崎は被爆地として、ローマ法王やマザー・テレサが訪れたこともあり、国際的なテーマの取材ができる町でした。その年は他紙や共同通信、NHKや長崎放送などに新人がどっときて彼らとの付き合いや競争も楽しかったです。給料をもらうようになったので、英語の勉強のために通信講座を始め、Foreign Affairsという英語の外交誌を定期購読しましたが、ほとんど読めませんでした。
—海外で記者を経験された期間が⻑いですが、どういった経緯で特派員として配属されたのでしょうか。
1983〜1987年に西部本社の社会部(当時は北九州市)に配属されました。当時、在⽇韓国人・朝鮮⼈には、外国人登録のために指紋押捺が強制されていたのですが、1985年ごろ人権侵害だとして全国的な押捺拒否運動や裁判が起きました。北九州や筑豊地方は、在日の方々が多く住んでいる地域で炭鉱跡もあり、植民地支配や戦争、戦後のつらい体験をした方々も存命で、歴史の爪痕も残っていました。在⽇韓国⼈・朝鮮⼈社会と深く付き合うようになり、さまざまな⼈権問題を知ることになりました。それが、初めての海外取材先が韓国になるというきっかけかもしれません。
—初めての海外取材について教えてください。
1986年、ソウル五輪の2年前に開催されたアジア⼤会の取材に社会部から派遣されることになりました。その頃NHKの韓国語講座が始まり、僕はビデオデッキを買い、会社の売店でNHKの講座テキストを定期購読しました。実際は警察まわりをしながらで、すぐ挫折したのですが、社会部長は僕が韓国語ができると誤解してくれたのだと思います(笑)。今考えてみたら、僕は社会部から⾏ったんですけど、スポーツ⼤会の取材でしたから、スポーツの記者が主で、少しはスポーツの取材もするんですよね。でも僕は、スポーツにはあまり詳しくないんです。午後8時開始の男子バレーボール中国対⽇本というゲームに派遣されました。日本の締め切りに間に合うためには午後9時には原稿を出さないといけないんですが、バレーボールの戦評をどう書いたらいいかわからなくて慌てました。記者席で隣にいた⽇刊スポーツの記者に「どう書いたらいいですか……?」とどこが肝か教えてもらって15行くらいの短い原稿を必死で送稿しました。こんな1ヶ⽉の韓国での取材経験でしたが、その翌年に外報部に異動することになりました。
—外報部配属後、アメリカ総局員としてワシントンに派遣されていますね。
外報部時代、アフリカや中東の要人、活動家、研究者、国連の幹部などのインタビューで何とかなると思っていた僕の英語ですが、ワシントンに行ったら全然英語がわからないんですよね。冷戦崩壊後の外交関係の話も難しかった(笑)。アメリカに着いた翌日に国務省の記者ブリーフィングに行きました。東西ドイツと米ソ英仏の4ヶ国でドイツ統一の方策を探る「2+4」構想について初めて明らかになった歴史的なブリーフィングだったのですが、最初の30分くらい何を話しているのかわからないのです。本当にこれはどうなるんだろうと思いました。その頃、ホワイトハウス、国務省、国防総省、議会の記者会⾒は、 2、3 時間後に内容が⽂字起こしされて送られてくるサービスがあったので、あとから辞書を引いて読むことはできるんです。会見に毎日出て、トランスクリプトを読んで慣れていくし、問題をよく知るようになると質問もできるようになっていきましたが、とにかく最初は大変なところに来てしまったと思いました。辞書を引くでしょ、「あ、今⽇この単語引いたの4回⽬?」ってことがあるわけです。挫折しかけたこともあります。
—その⼤変な時期をどう乗り越えましたか?
どうやって資料を効率よく早く読むかを考えました。全部⼀⽣懸命真⾯⽬にやっていたら夜が明けちゃいますから。時差の問題もあります。ワシントン時間のお昼頃に国務省の記者会⾒があるので、その中で何かニュースがあると、ワシントン時間の夜7時までには読んで理解して原稿を書いて⽇本に送らないと⼣刊に間に合わないんです。⼣刊の原稿を送ったら、次は⽇本の朝刊の原稿を書かないといけない。そうしていると、家に帰るのは午前 3 時過ぎぐらいになるんですが、シャワーを浴びてビールを一口含んだ頃に、「原稿直せ」という電話が東京からかかってくるんです。それを⽉〜⾦まで繰り返しました。当時は湾岸危機で⼟⽇には、欧州の要人がワシントンを訪れるので、へとへとでした。うまく⼿を抜く必要がありました。
—ワシントンから湾岸戦争に派遣されたそうですね。
1990年8月にイラクのクウェート侵攻で始まった湾岸危機は、1991年1月に湾岸戦争に発展しました。1⽉から3ヶ⽉間、サウジアラビアに派遣され、従軍取材をしました。サウジアラビアでは、⽶軍、イギリス軍、サウジアラビア軍、フランス軍などの多国籍軍が展開して、イラク空爆が続き、最終的に地上戦になっていくその過程を取材していました。湾岸危機で印象深いのは、日本の外務省が最後まで戦争は回避されると思っていた様子だったことです。私たちワシントンやニューヨークにいた日本メディアは、ホワイトハウスや国防総省、国連などをぴったりマークしていたので、かなり早くから戦争は避けられないとみていました。紛争や対⽴が起きた時に、権力者が戦争に持ち込むためには相⼿を悪魔のように悪く⾔って国⺠の憎悪をかきたてていきます。それがあの時に最前線で取材していた私たちには見えた。毎⽇国務省のブリーフィングに行きます。⼀番前にはアメリカの記者たちがいて、最初は冷静に、“Is the United States going to…?”「アメリカ合衆国はこうするつもりですか。」と聞いていたのに、ある日、“Are we going to…?”に変わったのに気づきました。「あぁ!」と思いました。戦争に突き進む国家がそこにありました。
—ワシントンで過ごす間に⼤変だった時期がたくさんあったと伺いましたが、どのように、またはなぜそれを乗り越えることができたのでしょうか?
助けてもらったということではないか、と今は思います。ワシントンには⽀局⻑含め記者が6人います。取材の手配やインタビューの録音起こしをしてくれる助手の人たちもいました。助手だった方たちとは今でも付き合っています。マイクロソフトの北京駐在の幹部だったり、国務省の官僚になったり、ケンブリッジ大で教員をしたり。東京の外報部にも助けてもらったし、それから結構外国の記者にも助けてもらったかな。アメリカの記者だけでなく、北朝鮮問題では、韓国人のワシントン駐在記者とも情報交換しました。競争相⼿じゃないですから、教えあったりもするし、助けてもらったというのが⾮常に⼤きいと思います。もう1つは、「これが終わるまで寝られない」とがんばるタイプではなく「まず寝る」という⾃分なりの習慣があったからかなあ。少し寝て起きたら「60分一本勝負」と言いながら原稿を書いた。原稿を夢の中で考えていたのかもしれません。
—アメリカ総⽀局の後はアフリカに特派員として派遣されていますね。アフリカで⼀番印象に残った取材について教えてください。
1994年4⽉27⽇に南アフリカの最初の全⼈種参加選挙が行われました。アパルトヘイト制度下で⽩⼈しか投票できなかった国で、人口の8割を占める黒人が初めて加わった選挙がやっとできたわけです。27年間獄中にいた反アパルトヘイト運動の闘士ネルソン・マンデラが、黒人と白人の交渉で平和的にアパルトヘイトを解消するために釈放されてリーダーになった。彼は 75 歳で生まれて初めて投票します。ダーバンという街の郊外の中学校の体育館でのことでした。⽇本⼈記者は僕と共同通信だけだったと思いますが、本当に真の歴史的瞬間だと思いました。アパルトヘイトという⽩⼈の⿊⼈差別を合法化しているシステムを、武力ではなく交渉で平和的な形に持って行って、投票で新しい国家をつくっていく。自分の原稿の書き出しを覚えています。「普通の人が普通に投票する。それを実現するのにこの国は本当に長い時間がかかった」。この一瞬は、暴力に満ち、たくさんの人が死んだ20 世紀の出来事としては極めて珍しく美しいことなんですよ。⼀緒に現場を見た共同通信の沼沢均ナイロビ支局長は、同じ年にルワンダ難民キャンプに取材に向かうチャーター機の墜落事故で亡くなりました。同僚が亡くなったというのは衝撃でした。
前編はいかがだったでしょうか?
後編では、川崎先生にとっての「人生と学び」とは何か、お話を伺います。