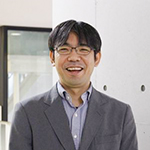人生と学び
人生と学び #21 - あらゆる「暴力」と向き合う 後編
「⼈⽣と学び」第21回後編では、前編に引き続き、元朝⽇新聞記者で、現在マスコミ論の授業を担当されている川崎剛先⽣にお話を伺いました。
前編での記者経験がどのように川崎先生の人生の学びにつながったのかについてご紹介します。
先生にとっての「人生と学び」
—先⽣にとって記者とは?
⾃分の役⽬は、読者が知りたいこと、読者に知ってほしいことを、代わりに取材して届けることだと思うんです。それが⾃分に任されたことで、アフリカだったらアフリカで、「今⽇のアフリカはどのように伝えようかな」っていうふうに思うし、やらなければいけないルーティンとかもあるけれど、代理でやっているんだという気持ちはありましたね。だから⾃分を伝えるというよりは、⾃分が代理で取材するという感覚でした。
—記者に求められる資質は何だと思いますか?
まず、⾃分のことを知るのは⼤事だと思うんです。あと、ある程度クールであることも必要だと思います。つまり、ちょっと⽬線を上げて、「なんでこの⼈はこういうふうに⾔うのか」と、客観的に、別の視点からみること。「これは許せない」とすぐ手をあげるんじゃなくて、別の形の⽬、別の⾃分をいつももっておくというのが必要だと思います。これまで僕らは統計を読むとか、ITを駆使するとか、科学について、ワクチンについて知っているとか、そういう勉強はあまりしてこなかったです。ジェネラリストというと聞こえがいいですが、「何でも一から聞く」という記者の育て方をしています。でも、もうそういう時代じゃないのかもしれないですね。だから、統計が読めるとか、財務諸表が読めるとか、科学やIT分野の知識といったものは今後すごく⼤事になってくると思います。それから、若い人のメディア・リテラシーに関しては、メディアの 現場でニュースや情報がどういうふうに⽣産されているか知っていることと、歴史の感覚をもっていることが必要だと思います。特に現代史についての感覚です。“The fourth generation forgets.”「第四世代は忘れてしまう。」という⾔葉があります。手触りの記憶と想像力は第⼀世代、第⼆世代までなんです。第四世代くらいまでの想像⼒をいつももっていてほしい。そうでなければ、ネットで検索してそのことについてパッとエキスは取れるけど、その脈絡は歴史にあるからわからないんです。そのこと⾃体を知らなくても想像できるような歴史への感覚をもっていてほしいと思います。
—先⽣が思う新聞社の意義、今後の展望を教えてください。
新聞社の意義は、その新聞社の資源である記者たちが、社会の問題や知るべきことを提⽰することにあると思います。基本的に新聞社は、現状とそれにまつわる問題を、読者の代わりに取材して届けるというのが役割です。それが今うまくいっているのかというと、いっていないと考えます。理由はいくつかあって、まずは、信頼が失われてしまっているから。「新聞は信じられない」とか、「マスゴミ」とか⾔われたりしていますが、それに対抗する強さがないような気がします。また、長年やってきたように記者を⼀⼈前になるまで5年かけて育てるということもできません。取材環境も変わっています。昔は、記者はみんな、⼈に会って名前や年齢を聞いて帰ってきたけれど、今はほとんど匿名でしか話を聞けないですし、ますますそうなっていく懸念があります。ニューヨーク・タイムズの次期CEOに49歳の女性が内定しましたが、⽇本の新聞社にはまだできそうにないですね。やっぱりこういうふうに変わらないと⽇本の新聞は危ないし、変わってほしいです。
とはいえ、マスメディアってまだいろいろな機能をもっていて、それはどの⺠主主義国でも⼤事な、残していかなきゃいけない社会の機能だと思います。今のジャーナリズムやマスコミの実態を⾒て、失望されてしまうこともあるけれど、「こうあるべきだ」という、メディア像みたいなものはみんながもっていてほしいです。SNSで個人が発信できるようになりましたが、それに比べてマスメディアは、チームで取材をして編集をしています。それはみなさん、つまり読者の代わりに取材しているんです。みんなが個⼈で発信できるのは悪いことではないし、ハッシュタグの多さが社会の声になることもあります。ですが、日常的にチームとして、見えないものを見ようとし、聞こえないものを聞こうとするジャーナリズムの機能は今後も重要だと思います。
—媒体が変わってもジャーナリズムという機能は残すべきということでしょうか?
そう!みんなはジャーナリズムといえば新聞と思っているけど、10年後は新聞紙じゃないと思いますね。放送局もずっと必要なものだと思うんだけど、今と同じワイドショーじゃないと思います。でも、形が変わっても、その機能は残さなければいけないものだと考えますね。今、現役の記者たちの間で、記者会見のありかたや、記者クラブのありかた、調査報道の方法などを研究する取り組みが行われています。コロナ禍で政治や経済の批判的な報道は難しくなっていると思うのですが、現役記者たちの改革と、それを受け止める社会の成熟を期待しています。
—では、先⽣にとって⼈⽣の学びとは?
アフリカで思ったことは世界の「暴力性」です。構造的な暴力が世界にはあります。歴史的にもそうでした。今の、“Black Lives Matter”も、世界の暴力を解釈しなおす運動ですよね。根底に暴力があるんです。他にも中国が⾹港の人びとの言論を抑えようとするような暴⼒、沖縄で基地に反対する⼈を排除するような暴⼒、それから⾔論で相手を黙らせてしまう暴⼒もあります。こういうあらゆる暴⼒というものがどうして無くならないのか、今になってもわからないし、無くなってほしいなと思いますね。⽇本⼈はそういう暴⼒に、構造的にさらされることが⽐較的少ないので、世界の暴力性に無関心でいられるのかもしれません。でもそのせいか、男性と女性の権力関係や、外国人や性的マイノリティーなどの少数派への差別に割と冷淡です。これも暴力ではないでしょうか。暴力には、武力であれ、権力による抑圧であれ、常に意識的でありたいと思います。あらゆるものが、暴⼒とそれに反撃するもの、つまり何らかの暴⼒で動いていることがすごく多いということを、記者経験を通じて気づきました。アメリカとアフリカの経験で、暴⼒と関わってから世界の構造を考えるようになりました。私の記者経験では、とにかく天安⾨事件以降の世界を考えると暴力がいろんな形で作用していたと思っています。
津田塾生へのメッセージ
—津⽥塾⽣の印象を教えてください。
僕の妹も津田塾OGです。また、僕は鹿児島県立鶴丸高校の出身なのですが、当時の鶴丸高校は津田塾を受験する女子が多かったんです。だからというわけではないのですが、津田塾生はまじめで優秀だと思います。
他の大学をあまり知らないのですが、ひとつ指摘したいのは、若い人の多くは、どこか「私は中⽴」という枠を作って、いろんなことに対して、この場所にいたい、この場所が“comfortable”なんだという場所を作っているような気がします。だから「賛成ですか、反対ですか?」って聞いたときに「⾃分は中⽴です」と考えたがることが多いのではないでしょうか。要するに、中⽴という、考えの場所を決めておいて、⾃分はここにいる、いたい、そういう⾵に⾒られたいという⼈が多くなってきているのでしょう。自分が少数派だと規定するには実力が必要だから、多数派になりたいですよね。さまざまな事象で判断の材料を与えてくれるはずのメディアの弱体化も影響しているでしょう。
今の話と矛盾するようですが、津田塾生は、ジェンダーについての関⼼はとても⾼いですね。でも、あまり国際政治には関⼼がなかったり知らなかったりします。⼀番驚いたのは、授業で「朝⽇新聞にはこういう⽀局があります」という話をしようとして、最初に「イスラマバード」と⾔った時に、みんなが「知らない」って⾔ったことです。それは本当にびっくりしました。アフガニスタン取材の拠点として特派員を置いているのですが、今の20歳くらいの学⽣は「イスラマバード」とか「アフガニスタン」というものを知らないんだとわかった時に、これはもっと伝え⽅を考えなきゃいけないと思いました。
—津⽥塾⽣へのメッセージをお願いします。
アメリカのジャーナリストで歴史家のデービッド・ハルバースタム(David Halberstam)が90年代の初めに来日して講演したときに、日本の若者へのメッセージを聞かれました。そのときの短い答えが印象に残っています。“Read a little more” 。まだインターネットはなかったけれど、テレビやゲームなど、人びとの時間は新しい娯楽にどんどん取られていくそのとき。「忙しいだろうけど、本も読んで。もう少しだけ」という呼びかけだと思います。新型コロナウイルス「COVID-19」で2020年以降の社会は変わらざるを得ないでしょう。どう変わるのかまだわからない。「ドーセバカイズム*」のような態度でなく、真面目に向き合っていってほしいと改めて思います。